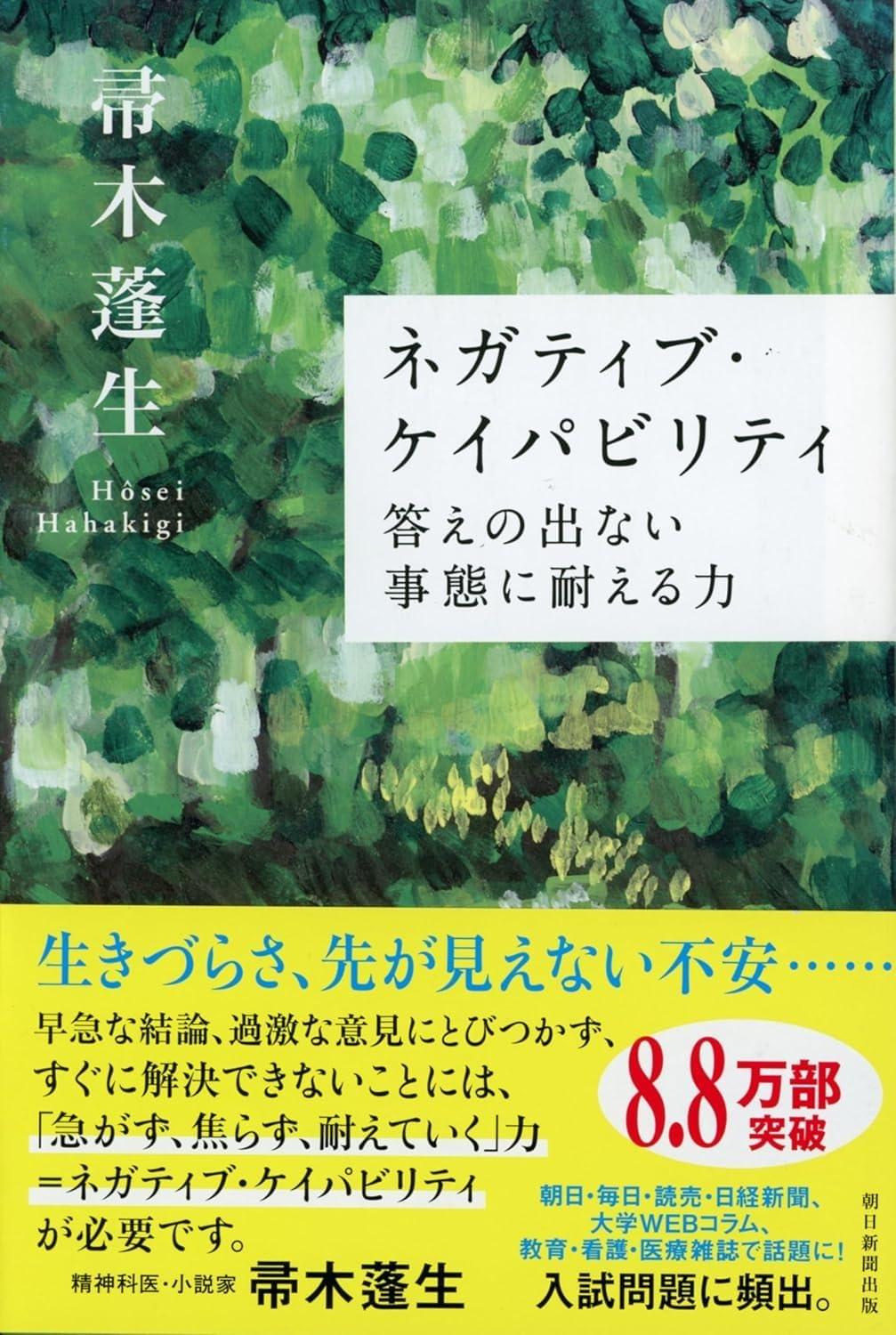「生きるべきか、死ぬべきか。それが問題だ(To be or not to be, that is the question.)」
というシェイクスピアの『ハムレット』の台詞、多分どこかで誰もが一度は耳にしたことがあると思います。
しかし昨今のこの混沌とした世の中、To beでもnot to beでも決められない事柄、多すぎますよね。
この本『ネガティブ・ケイパビリティ 答えの出ない事態に耐える力』はイギリスのロマン派の大詩人がシェイクスピア作品から見出した『ネガティブ・ケイパビリティ』について書かれた1冊です。
詩人キーツ、文豪シェイクスピア、そして(私が大好きな)紫式部の源氏物語などが詳しい説明とともに取り上げられていて、精神的とか心理的とかの話だけではちょっと…と言う人にもお勧めの1冊です。
身近なところでは、不登校問題、セラピー犬、現代教育やマニュアルに慣れた脳の限界…「あるある」がそこかしこに詰め込まれています。政治・宗教・戦争についても書かれていて、まさに今、読んでおくべき1冊でもあります。
ネガティブ・ケイパビリティとは一体何なのでしょうか。
それは『拙速な理解ではなく、謎を謎として興味を抱いたまま、宙ぶらりんのどうしようもない状態を耐え抜く力』です。
『ネガティブ』とついているので、何か良くないものかな感はあると思いますが、タイパ、コスパと言う概念が満ち満ちた今の世の中、起きた問題を性急に、生半可な位置づけや知識で持って、未解決の問題にせっかちに帳尻合わせをしがちです。
そこをグッと踏みとどまって、To beでもnot to beでもない状態を持ち堪えていく、それがこの『ネガティブ・ケイパビリティ』なのです。
私たちにとって、わけのわからないこと、手の下しようのない状況は不安であり、早く何とかしたくなるでしょう。
けれど、この『ネガティブ・ケイパビリティ』を身に付けることで、そこで拙速にならず、ぐっと踏ん張る力を身につけることができるのです。
この本には、シェイクスピアにこの力が備わっていると発見した詩人キーツ(その生涯が『ブライト・スター いちばん美しい恋の詩』と言う映画にもなった、こよなく美しい詩を生涯書き続けた大詩人です)と、第二次世界大戦に従軍し、波乱に満ちた戦場を経験した精神科医ビオン(この人の人生もなかなか興味深いのですが)の生涯についての解説がまず記されています。
そして『ネガティブ・ケイパビリティ』の考え方が様々な医療に使われていく様子、芸術との関係、特に紫式部の『源氏物語』において発揮されている様子、そして『解決することこそ大切』、と教わる教育の場で、教育者が必要とする『解決できないこと』に向かう姿勢(問題から解答がすぐに出る事柄なんて人生のほんの一部です)、宗教、政治の中にいかにこのネガティブ・ケイパビリティが必要かが書かれています。
「解決すること、答えを早く出すこと、それだけが能力ではない。解決しなくても、訳がわからなくても、持ちこたえていく。消極的(ネガティブ)に見えても、実際には、この人生態度には大きなパワーが秘められています」
(本文P200〜201)
最近世の中の政治や教育、メチャクチャになってきてない…? とか、SNSやってると何かこう、思いやりとか寛容さとか明らかに、それも全体的に足りてないよね…? とか、頭を抱えることが少なからずあると思います。
そういう時にこそ、拙速に物事を決めず、解決できない問題を耐える力『ネガティブ・ケイパビリティ』は役に立つのです。
何故なら、「どうにも解決できない問題を何とか耐え続ける力」こそは『寛容』に、ひいては『平和』にも繋がっていくものだからです。
『寛容』は大きな力ではないけれど、寛容がない場所では何事も物事が極端に、過激に進んでいってしまうからです。
世界中で今起きている諸問題、どれもが『不寛容』に基づくものになっている、と私は感じます。悲しいニュース、腹の立つニュース、何でもかんでも拙速に決めては混乱を招いてくる(主に)政治ニュースのあれこれ。
それらが怒涛のように押し寄せてくるこの世の中、息のしやすい世界に身を置くためにも、『ネガティブ・ケイパビリティ』というこの言葉と概念を覚えて、心のお守りにするのも良いでしょう。
最近なんか、テレビも新聞もSNSも、どこをみてもなんかしんどいな…という人ほど、この一冊を是非手に取ってみてくださいね。
寛容があるところには共感もあり、世界はTo beだけでもnot to beだけでもないのです。
@akinona